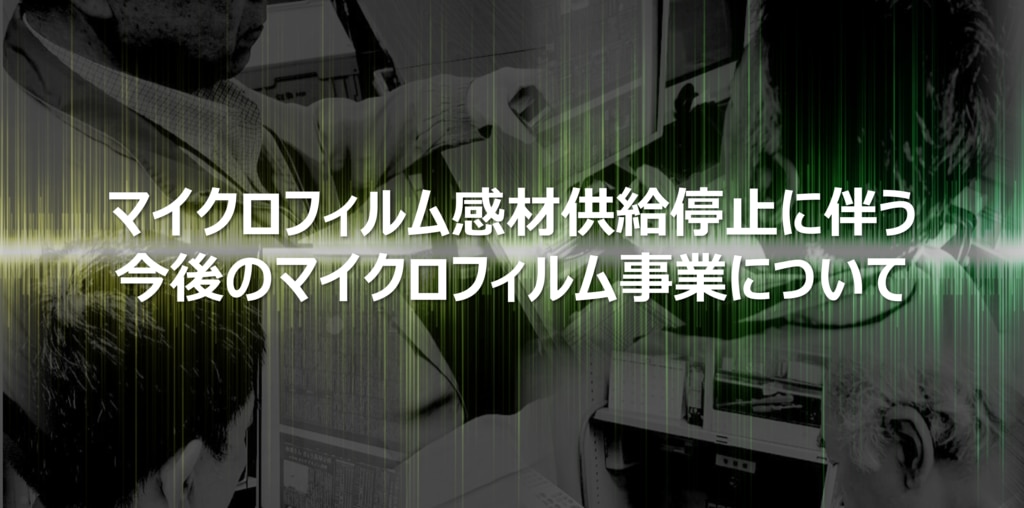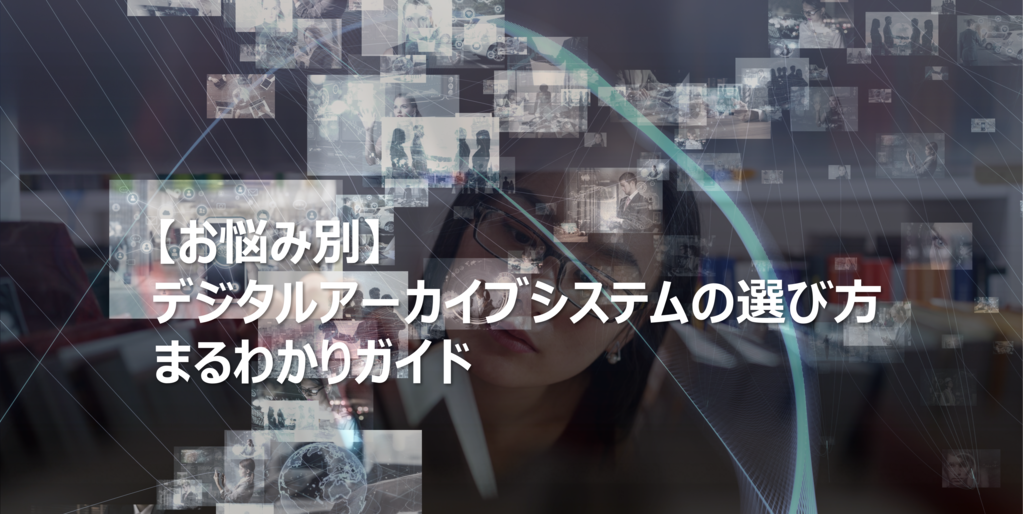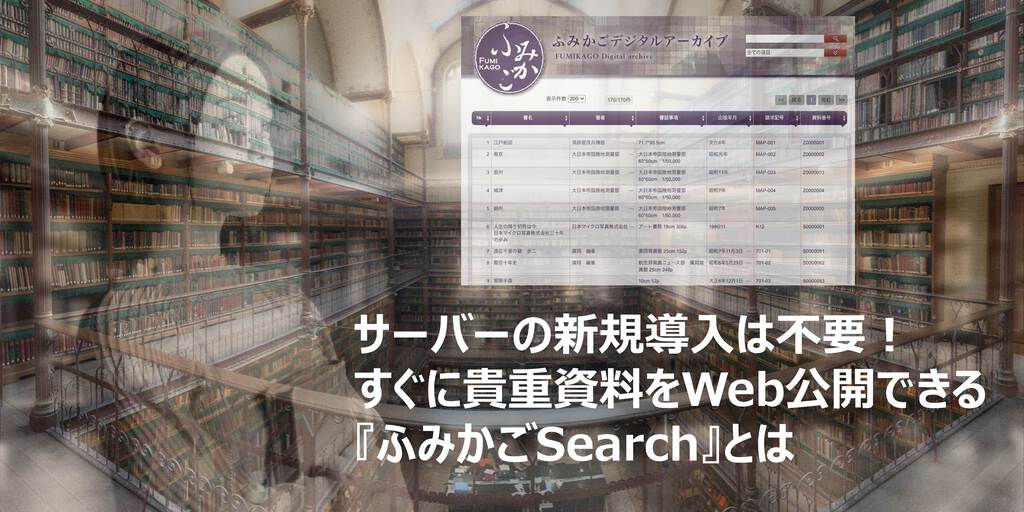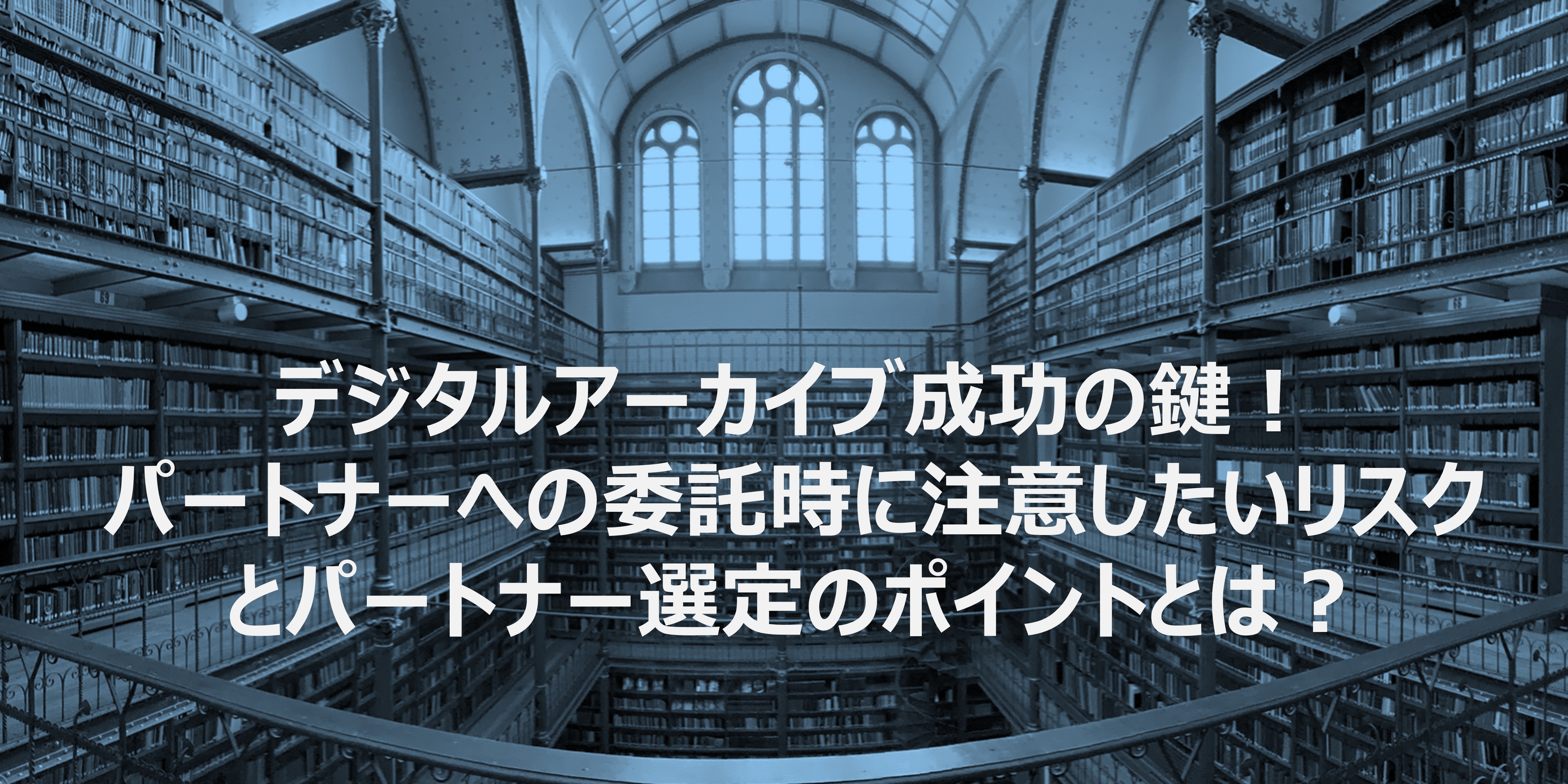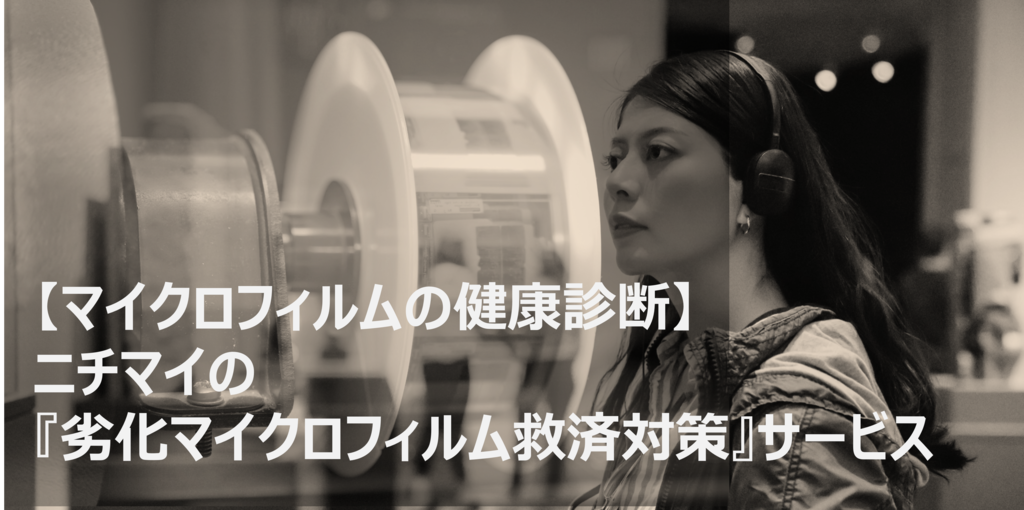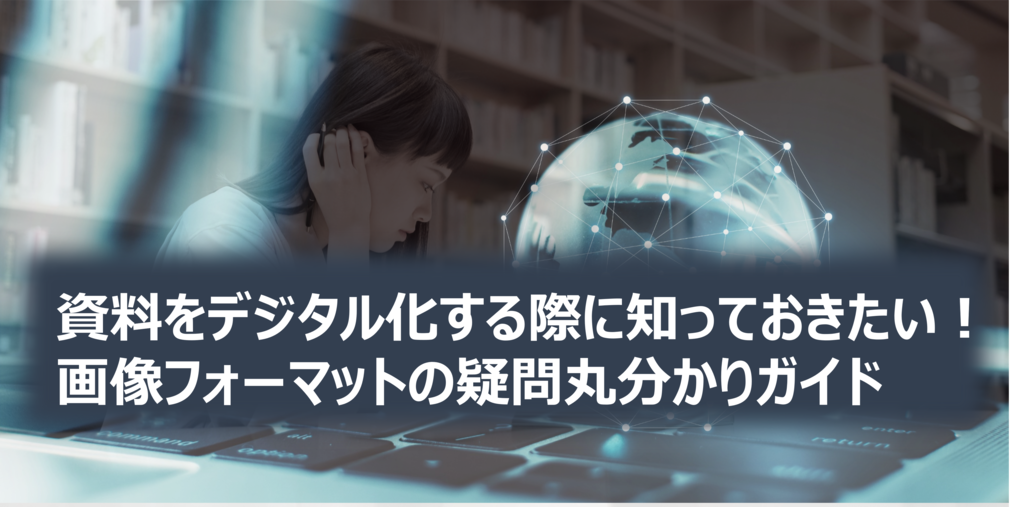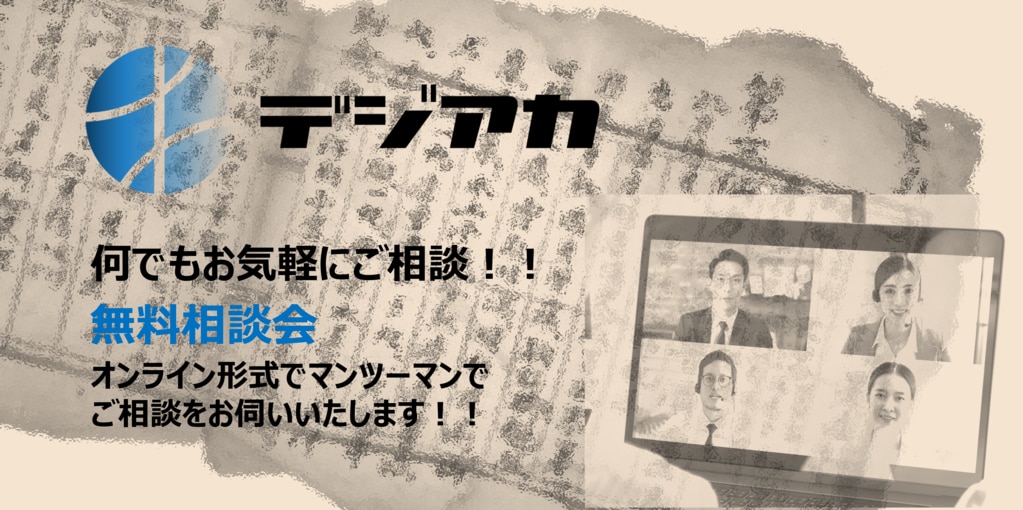マイクロフィルムの供給停止までに準備しておきたいこと
マイクロフィルムの材料の供給停止が、製造元である富士フイルム株式会社より発表されました。今年(2025年)12月がマイクロフィルムの材料に関する最終受注受付の締切となります。
https://www.fujifilm.com/jp/ja/business/data-management/microfilm(富士フイルム株式会社ホームページより該当ページ)
これに伴い、マイクロフィルムの作製(撮影)や所有しているマイクロフィルムの複製が数年後には実施することが難しい状況となってきました。
現在行っているマイクロフィルム業務、また今後計画されているマイクロフィルム業務について、最終受注受付の今年の12月までに行うべき準備などは、どのようなことがあるでしょうか。
今回はマイクロフィルム供給停止までに準備すべきポイントをまとめました。
目次[非表示]
マイクロフィルムは、長期間にわたり安定して保存可能なことや、原本性(マイクロフィルムの情報を改ざんすることはほぼ不可能で)に優れていることから、デジタル化が主流となっている現在も紙資料の媒体変換メディアとして採用されています。
しかし、マイクロフィルムの材料供給が停止されることとなり、マイクロフィルムの作製や複製といった関連業務については様々な検討や見直しが必要なってきました。
前述の通りマイクロフィルム材料に関する受注締切は今年の12月となりますので、少なくとも11月頃までには検討や見直しをある程度終えておく必要がありますが、検討事項が多く、どこから手を付けてよいか悩んでしまうのではないでしょうか。
今回は、マイクロフィルムの供給停止までに検討や見直しなど準備しておきたいことをまとめましたので、確認していきましょう。
1.マイクロフィルムの業務はいつまで行えるのか?
マイクロフィルムの材料供給停止に伴い、最終受注受付の締切は今年の12月となりましたが、今年の12月でマイクロフィルムの作製(撮影)や複製が行えなくなるわけではありません。
マイクロフィルムの業務が継続できる期間については、マイクロフィルムの材料を利用してマイクロフィルムの業務を行う各会社さんのマイクロフィルムのサービスを継続する期間が関係していきます。
つまり、マイクロフィルムの業務がいつまで続けられるのかについては、マイクロフィルムの業務を委託する会社さんが「○○でサービスの提供を終了します」という期間ということになるので、各会社さんの方針次第ということになります。
各会社さんの方針となるので、いつまでにマイクロフィルムの業務が行えなくなると断定することはできませんが、マイクロフィルムの材料は製造されてから約2年程度で使用期限の目途となるので、最終のマイクロフィルムが製造されてから数年で順次終了されていくことが予想されます。
マイクロフィルムの業務がいつまで継続できるか検討するためには、現在マイクロフィルムの業務を委託している会社さんに確認して今後の計画を立てるようにしましょう。
「当社のマイクロフィルム感材の販売終了とそれに伴う弊社の対応について」
2.マイクロフィルム作製(撮影)業務で準備しておきたいこと
1)継続してマイクロフィルム作製業務を行っている場合
現在マイクロフィルム作製業務を継続的に行っている場合には、以下の準備を進める必要があります。
①マイクロフィルム作製業務を継続するか、もしくは中止するかの検討
②マイクロフィルム作製業務を継続する判断をした場合、いつまでマイクロフィルム作製業務を継続するか検討し、併せてマイクロフィルム最終発注に向けて必要となる数量を把握するために、マイクロフィルム作製対象となる資料がどの程度になるか調査する
③マイクロフィルム作製業務を中止する判断をした場合、マイクロフィルム作製業務に代わる電子化等媒体変換案件の必要性の検討をおこなう
2)新規マイクロフィルム作製を行う場合
マイクロフィルムの材料供給があるうちに、マイクロフィルムの作製を行うことを検討する場合もあると思います。
新規でマイクロフィルムの作製を行う場合には以下の準備を進める必要があります。
①マイクロフィルム作製の対象となる資料の選定
②マイクロフィルム作製を委託する業者さんの選定
③マイクロフィルム作製の為の仕様書等の作成等
④マイクロフィルム作製を委託業者に資料を預けておこなうか、資料保管施設に出張作業で行ってもらうかの検討
1)、2)ともにマイクロフィルム作製業務を行う委託業者さんに相談して準備、検討をすることをお進めします。
3.マイクロフィルムの複製業務で準備しておきたいこと
所蔵しているマイクロフィルムの複製を継続的に行っているもしくは、新たに複製することを計画している場合、多くは所蔵しているマイクロフィルムが劣化していて複製が必要であるということではないでしょうか。
ここでは、複製の対象が劣化しているマイクロフィルムと想定した場合のマイクロフィルムの複製業務に必要になる準備ポイントをまとめました。
1)複製対象となるマイクロフィルムを選定する
→他機関で同じマイクロフィルムを所蔵していないか。他機関で同じマイクロフィルムを所蔵しているのであれば、複製対象から外すことを検討する。
→他機関で同じマイクロフィルムを所蔵していない場合、マイクロフィルムに収録されている資料は現存しているか確認する。マイクロフィルムに収録されている資料が現存していない場合には、マイクロフィルムがオリジナル資料と同等の意味を持つ場合がありますので、優先して複製すべきか検討する。
2)マイクロフィルムの劣化がどのくらい進んでいるか把握する
劣化が進行している場合には、優先して複製すべきか検討する。
3)マイクロフィルム複製業務の対象となるマイクロフィルムの数量を把握し、複製業務をどのくらいの期間で行うか検討する
4)マイクロフィルム複製業務の仕様書等の作成等
マイクロフィルムの複製業務についても前項2)と同じくマイクロフィルムの複製業務を実際に行う委託業者さんに相談することをお進めします。特に劣化しているマイクロフィルムの複製業務については、専門的な知識や技術が必要になることがありますので注意が必要です。
4.マイクロフィルム業務の代替業務の検討も進めましょう
マイクロフィルムの作製業務も複製業務も数年後には実施することが難しい状況となります。
マイクロフィルムの各業務の実施が終了した時に慌てないように、今からマイクロフィルムの各業務に代わる媒体変換業務も併せて検討していくことも大切です。
マイクロフィルムの代替業務として、費用面や品質などを考慮すると、有力な候補はやはりデジタル化業務になってくるのではないでしょうか。
マイクロフィルムの代替業務として、デジタル化業務を選択した場合、以下の準備が必要になると考えます。
1)デジタル化業務をいつから行うか、開始時期の検討
2)マイクロフィルム文書による文書規定やセキュリティ規定が運用されていた場合には、デジタル文書による運用を想定した文書規定やセキュリティ規定等の見直し
3)デジタル化業務を行うための仕様書及び委託業者さんの選定要件の検討
マイクロフィルム業務をデジタル化業務に移行するといっても、決めないといけない事項が幅広く専門知識も必要になる部分も多くあります。
資料のデジタル化やマイクロフィルムのデジタル化を専門的に行っている経験豊富な委託業者さんにデジタル化業務の進め方等を確認してみることをお勧めします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
マイクロフィルムは長期保存が可能な媒体のため、マイクロフィルム関連業務も長期にわたり実施や計画がなされており、多角的な検討や準備が必要になりしっかりと対応したいところです。
しかし、多角的な検討や準備が必要なのに、今回はその検討や準備の期間も短く、担当された方だけでは悩んでしまうこともあるのではないでしょうか。
当社では創業以来70年以上にわたりマイクロフィルム関連サービスを提供しており、豊富な実績と経験で皆様のお悩みを解決してまいりました。
マイクロフィルムの材料停止に伴う様々なご質問お悩みがございましたら、当社へご相談ください!
マイクロフィルムの感材供給停止に伴う関連記事については、こちらもご参照ください!